
第20週:TRAFFIC / THE LOW SPARK OF HIGH-HEELED BOYS

トラフィック、1971年発表の5枚目のアルバム。
この変形ジャケットは今でも人気のひとつなのだが、中身の方の人気はと言うと・・・・
当時から散々な評価を受けている作品でもある。私は、これを最初に聴いたせいもあるだろうが、
非常に大好きなアルバムで、やっぱり前作が『ジョン・バーレイコーン・マスト・ダイ』という傑作なので
しょうがないのかな、と思うと同時に、少々このアルバムが可哀相に思えてくる。
私が捻くれているせいもあってか、散々な評価しか受けていないアルバムは何故か妙な親近感を感じ、
ついつい買ってしまう。前作が傑作となると尚更だ。
散々な評価しか受けていない、とは言っても2曲目のタイトル曲は今でもトラフィックの代表曲でもある。
ゆる〜い感覚と、非常に耳に馴染み易いジャズの要素、いつまでも聴いていたいと思わせるような曲だ。
その他の曲も、まとまりのなさはあるものの、トラッド色はもちろん、非常にリラックスした演奏、
何よりも実に英国らしい。(アメリカで売れたらしいが。)
まぁ、私が今更こんなとこで何を言っても評価は変わらない。というわけで、タイトル曲のためだけにも
是が非でも買ってもらいたい。なかなかこんな気持ちの良い曲はない。お薦め。
第19週:DÆVID ALLEN / EAT ME BABY I'M A JELLY BEAN 〜sings jazz
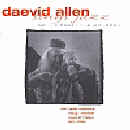
SINGS JAZZということで、これは御大デイヴィッド・アレンの1998年リリースのソロ・アルバム。
ジャズのスタンダードをアレン自らが歌ったもの。選曲も非常に興味深いところで、メジャーな
ところでは、マイルスのSO WHATや、チャーリー・パーカー、ガーシュイン他等。歌詞もアレン自らが
変えたり、作ったりして歌っている。周知の通り、アレンの原点はジャズにある。言わば、アレンの
ルーツとでも言えるようなものである。ジャズにアレン流のユートピア思考を塗したようなアルバム。
それにしても、アレンの声はホッとする。ゴングにおいてもそうだったが、ここで聴かれるものは
ロックでもない、紛れもないジャズである。そんな落ち着いた空気の中で聞けるアレンの声は格別だ。
特にSO WHATでは、アレンの詩がとても良い。原曲は歌詞無しだが、(原曲はMILES DAVIS/KIND OF BLUEの1曲目)
アレンらしい皮肉的な歌詞が楽しめる。
前回のチェット・ベイカーもそうなのだが、嫌なことを忘れさせてくれるアーティストは私の中でかなり大きい。
多分に逃避的なものなのだが、そうでもしないとやっていけない。
第18週:CHET BAKER / SINGS AND PLAYS

チェット・ベイカーの歌モノで人気なのは、シングスとこのシングス・アンド・プレイズである。
対のような作品だが、どうやら内容、評価はシングスの方に軍配が挙げられているようだ。
この作品は、ストリングスも導入してかなりポップ的な側面が覗える。ジャズというより、
より大衆受けしそうなポップさが特徴なのだが、チェット・ベイカーのヴォーカルが乗ると、そこには
やはり独特な世界観が確立されていて、不思議な感覚がある。そして、チェット・ベイカーのトランペットも
絶妙のタイミングでなんとも繊細なプレイが聴ける。これはおいしい。
昨日の晩、酒を飲みフラフラとしながら家に帰ってきたのだが、ちょうどこのチェット・ベイカーの
シングス&プレイズをかけると頭のフラフラさとチェットと気だるいヴォーカルが心地良く、不思議な
世界の中にいるようだった。そこからは記憶にない。(起きた後は最悪だった)
聴いている間だけ、幸福感を味わい、その後の時間は現実に連れ戻されるというシンデレラのような盤。
30分間の幸福。
第17週:ROGER WATERS / AMUSED TO DEATH
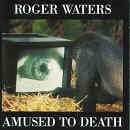
再び、ロジャー・ウォータースのソロ。邦題:死滅遊戯。ロジャーはピンク・フロイドの
時代から、様々なコンセプトの元、アルバム作りを行ってきたが、狂気、アニマルズ、ウォールから
続く、お得意の社会風刺アルバム。コンセプトは『情報とそれに支配される人の様子』を
描いたもの。思想面では、ロジャーの集大成とも言えるべき内容で、非常に重い。
曲も相変わらずナイフのような痛々しいものから、すっきりとしたロック的内容も相まってバラエティ感もある。
ジェフ・ベックが全面的にギター参加しているのも大きい。
それにしても、この『情報に支配される人々』というコンセプトは現代において、かなり重い。
例えば、マイケル・ムーアの『ボウリング・フォー・コロンバイン』において、アメリカの銃社会の成り立ち、
政府とマスコミメディア、CMの関わりが描かれていたのを思い出す。(死滅遊戯は92年発表だが)
簡単に言えば、メディアによるプロパガンダということなのだろうが、この世論操作こそ政治の一番重要な
手法であることを訴えている。
今の世の中、何を信じていいのか全く分からないが、ロジャーの考えでは『市場という概念において、
全てが奇跡のように巧みに企てられ、そこに信じれるべきものは何もない』ということなのだろう。
私が思うことは、ヒエラルキー的な物事に対しては、信じるな、距離を置け、という事だけですが。
そういえば、TOOLは『テレビを消せ』と言ってましたね。
第16週:C.A.QUINTET / TRIP THRU HELL

これもあまり、お薦めできない作品。ジャケからしてB級臭さがプンプンと
漂い、聞いてみても実際B級感は拭えない。(好きな人ごめんなさい)
音質が悪いのが功を奏して(?)、アルバムのコンセプトともなっている
頭の中(想像の中)での地獄巡りは、ある種の臭みと同時に届けられている。
表題曲は、PART1,PART2構成でやや長尺。ご機嫌なフレーズから、これまた
胡散臭さの極みとも言えそうな女性コーラス。懐かしさ(歌謡ぽさ、古臭さ)を思わせるサックス。
展開もややぎこちなく、編集感覚もある。(コーラスから、急激な展開のドラム・ソロ)
この編集感覚はひょっとして、アモン・デュールのサイケ・アングラ?このアルバムは
サイケデリック・アンダーグラウンドと同じ年、1969年。
サイケ・アングラが、正真正銘なドラッグによる"バッド・トリップ"的なアルバムだとすると
これは、麻薬だと信じ込ませられ喰わされ、実はただのキノコ、小麦粉で、トリップした気になる
ヒネクレサイケである。
読み返してみると、なんだか悪口ばかり書いているようだが、こう言ったB級臭さを愛して
病まない素敵な方には、素敵なアルバムになることは間違いない!
第15週:AIMEE MANN / LOST IN SPACE
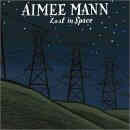
さて、珍しく最近チックなものを。
最近と言っても、2年前ぐらいだと思われる、元ティル・チューズデイのエイミーマンの
アルバム。
とは言っても、私はエイミー・マンもティル・チューズデイも、映画『マグノリア』も何もかも
知りません。何故買ったかと言うと、ジャケに惹かれて。。
寂しそうな雰囲気に何故かピーンときた。内容は、ビートルズ直系(?)とも思わせるメロディアスなもので
でも、なんとなく気だるそうに歌うエイミー・マンの声は心地よいし、よく言われるように
優しさも感じられる夜向けな音楽。
尚、国内盤には映画『アイ・アム・サム』(これももちろん見てない)に挿入されたビートルズのカヴァー
『TWO OF US』がボートラで入っている。
プログレのプの文字もないが、プログレに疲れた時はよく聴いている。
変なモノ好きな人にはお薦めできませんが、気がむいたらどうぞ。
第14週:HEINER GOEBBELS / SHADOW/LANDSCAPE WITH ARGONAUTS

ハイナー・ゲッベルスはあのカシーバーで活動し、またアルフレート・アルトとのデュオなど、数々の
作品をリリースしてきた奇才である。
このECMから発売された彼のソロ作品はもちろん彼の代表アルバムである。
ECMといえば、個人的にキース・ジャレットやパット・メセニー等ジャズ、フュージョン系の
アーティストを思い浮かべてしまうが、この作品はジャズでもフュージョンでもロックでもない。
街行く人々の会話、車の音、騒音、そこから音楽に繋がっていくという、一大絵巻。
人々の行き交う音、会話が音楽になってゆく様は凄いの一言だ。
歌詞(言葉)は、ハイナー・ゲッベルス自らの詩とエドガー・アラン・ポーの詩が交差する。
歌はSUSSAN DEIHIM(イラン生まれらしい)の民族色豊かな歌声が響き、それを遮断、または
繋がるように再びボストン市街の人々の会話等に移ってゆく。
ウォークマンを聴きながらでは得られない感覚が、この編集にはある。
ちなみに、チャールズ・ヘイワードも参加。
第13週:ROGER WATERS / IN THE FLESH

現在のフロイドに賛否両論があるように、ロジャー・ウォーターズにも
賛否両論があり、フロイド・ファンとしてはかなり複雑な思いをしている方も多々いらっしゃることでしょう。
個人的には、現在のフロイドも好き、ロジャーのソロも、らしくて好きという曖昧な感じ。
現在(と言っても活動停止中!?)のフロイドは、フロイドの魅力の一つでもあるデイヴィッド・ギルモアの
ブルース・フィーリング溢れる泣きのギターを中心とするやや回帰的なものである一方、(もちろんそれだけではないです。)
ロジャーの方は、アニマルズ辺りから強くなってきた社会批判を主として、女性ヴォーカルを迎え
非常にソウルフルなものを展開している。
フロイドの曲も演奏許可が下りたと言う事で、このライブ盤は決定的なベストとも言える。
同じ曲を演っても、これだけ決定的な温度差があるとやはりこのロジャーとフロイドの面々が袂を分かれた事に
納得してしまう。
しかし、やっぱりロジャーの声は力強い。力強く、そして弱い。
この弱さが、現在の人間の進んでいる道に対する嘆き、諦め、絶望のようで面白い。
フロイド時代からの選曲にしても、ロジャーのソロ曲にしてもここでは全く違和感なく
溶け込みあっている。
完璧なまでに、ファンの願いを一刀両断にするアルバム。(ファンの願いとは、もちろんロジャーがフロイドへ戻るということ)
そして、ロジャーの自伝的アルバム。
第12週:CHICK COREA / RETURN TO FOREVER

フュージョンの金字塔としてその名を現在においても確立している。
フュージョンと言えば、最近のリスナーはあまり良い印象を持たないかもしれない。
安っぽいスーパーでかかっているようなBGMのようになってしまった感がどうも頭の中にある。
しかし、ここから流れてくる音は決して古びることのない透きとおった音だ。
フュージョンでは、マイルス・デイヴィスの60年代後半からロック的なダイナミズム、ファンクっぽいノリを
加えたものが、その走りとされるが、やはりこのチック・コリアのリターン・トゥ・フォエヴァーをその完成
と見るべきだろう。(いや、あまりそんなのはどうでもいい。)
ジャケットの美しさに先ず目を奪われる。
広がる海。水平線。カモメが海の上を飛翔してゆくその姿。
あまりにも劇的な幕開けである。音も静かに海を飛翔してゆくカモメの動きのようでもある。
不思議な空間に包まれ、それは非常に心地良いものだ。
もちろん、このリターン・トゥ・フォエヴァーの音楽がカンタベリー・シーン等、(否、音楽全体に)凄まじい
影響を与えたのは周知の事実だろう。
それにしても、なんとも言えない美しさだ。
第11週:LOU REED / ROCK N ROLL ANIMAL

73年ニューヨークでのライブ音源。
ヴェルヴェット時代,トランスフォーマー、ベルリン期のルー・リードから想像し難いこの音。
アリス・クーパーのバック・バンドを従えて録音された。正直私も最初聴いた時は違和感を持った。
ハード・ロックである。そしてジャケットはグラマラス。
ルー・リードの魅力なんて沢山ありすぎて、実はよくわからないのかもしれないが、
音痴なのかわざとなのかよくわからない音程だと思っている。
怒るように吐き出される一つ一つの言葉が非常に退廃的で格好良い。
ヘロインでのスピードを増して突き進んで行くこの感覚は正直鳥肌ものだ。
暗い感覚で『How do you think it feels?』と突きつけてこられる感覚は、なんとも言えぬ快感を覚える。
バック・バンドの演奏は正直硬質で非常にカチっとしており、安心するのだが、ルー・リードの声で一気に崩れる。
このアンバランス感が凄まじい。非常に危ない、ギリギリのスリル感を味わえる極上のアルバムだ。
ところで、キャロラインのはなし<1>の声、いくらなんでも音程凄すぎません?わざとかな。