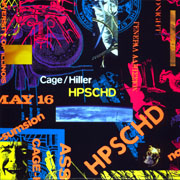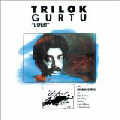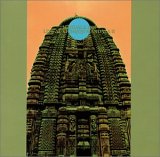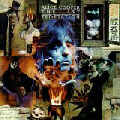|
いつかこの項にクロームを登場させねばなるまい、と思っていたが、それが遂に実現の運びとなった。というのも、クロームのような音は錚々月に何度も聴くような類の音ではなく、年に二、三度がせいぜい関の山と言ったところで生理不順な女の子のように私の頭が欲する時期とタイミングがズレまくって今に至る。年に二、三度と言っても必ずしもそれが音楽的価値とイコールすべきものでないのは聴いたことのある人なら分かって頂けるだろう。 クロームが登場したのはおそらく1976年。パンク・ムーヴメントの潮流と時期が重なったせいか、ニューヨーク勢の影に隠れる形となったが、西海岸ではレジデンツ、タキシード・ムーンと並び最重要バンドであった。ヘリオス・クリードの鳴らすそのギターは轟音ではないが、無表情に鋭くノイジーなオシレーターと化し、一体何をやっているのか分からないデイモン・エッジのシンセ等はあまりにも無意味すぎたし、ドラムはシンバルレガートもクソも無く気分まかせ、最大の極みは「おい、こら。エンジニア呼んでこい!」と言いたくなる録音の不安定感。これらがアモン・デュール1stのようにカオス的均衡を齎した編集術により我々にこの盤の重みを実感させた(いくらかの歳月が必要だったにせよ)。 クロームの存在は「恣意的邂逅」の実践に尽きる(彼らが意識していたかどうかに関わらず)。想像は誤解を呼び、或いは誤解を逆説的に呼び込もうとする彼らの嗅覚は凡庸極まりない一部のパンク勢と比べ明らかに抜きん出ていた。そしてパンクの一部にするには余りにもメッセージ性に欠けていたし、また、マスメディアが利用するドラマ性は無に等しかった。悪夢の断片のような音の連なりが、皮肉にも唯一のメッセージ(安易なムーヴメントに対する)となった。 ほとんどの作品が入手難という異常事態ではあるが、難無く入手できるこのアルバム(ALIEN~とのカップリング)とアンソロジーは必携である。 |